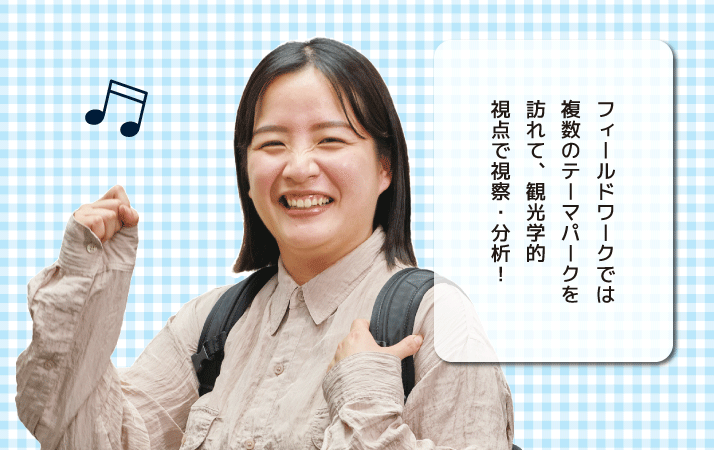社会学部
現代社会学科

観光学ゼミでは、インバウンド観光を支える成田国際空港へ。同空港の施設や歴史について学び、国際観光・国際空港のあり方を考える機会に。
観光スポットをめぐり、SNSに写真をアップするだけが旅行の楽しみ方ではありません。その場にいるからこそ出会える時間と体験とを味わいつつ、日常と非日常のギャップや、リアルとフィクションのつながりを楽しむなど、それぞれの「新しい観光」を楽しむ人たちが増えています。観光学では、観光関連産業の研究、あるいは観光とまちづくり、観光化が地域に与える影響といった視点から「観光」について理解を深めます。
本ゼミナールではさらに、ホスピタリティ、地域コミュニティや国際社会のあり方など、関連領域へと学びを広げます。またフィールドワークでは国内外の観光地、テーマパーク、駅・空港などを訪れ、関連業界の取り組みを調査。世界遺産や鉄道、アニメなどをテーマにした「観光まちづくり」についても学びます。
観光客を呼び込む手法の検討、観光プラン作成にも挑戦し、地域・関連業界とともに新しい観光を「共創」する学びに取り組みます。

崎本 武志 先生
学生時代とは「生きるを学ぶ」貴重な人生の1ページです。好奇心を持ち視野を広くして、あらゆる事柄の森羅万象を追求しましょう。
Student Interview
世界自然遺産に興味を持っていることから、2年次には環境について特に学びました。その中で注目したのは、環境問題と観光が密接な関係にあること。そこで、観光学の観点から環境を学んでみようと思いました。「観光」の魅力は、いろいろな分野の学びや、社会の動き・変化と広く関わっているところだと思います。今後は特に、自然災害によって被害を受けた地域などで進められる「観光による地域復興」に注目して学んでいきたいと考えています。