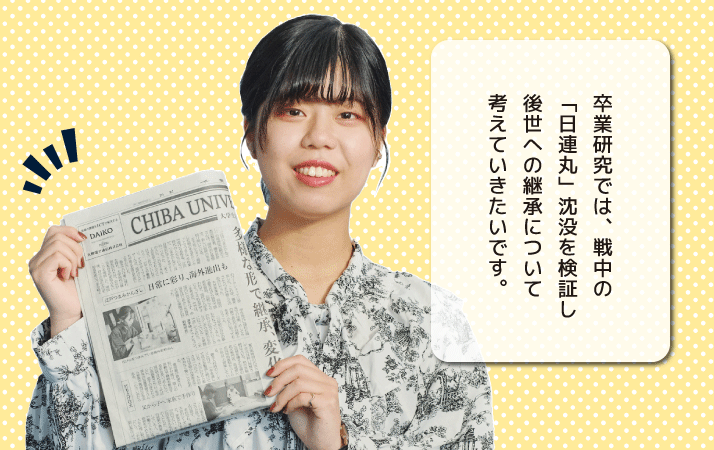メディアコミュニケーション学部
マス・コミュニケーション学科

メディアの制作を実践して学ぶ機会が充実。神田洋先生の授業では、スポーツニッポン新聞社の協力を得て、紙面制作に取り組む。
社会の役に立ち、人々の共感を呼ぶような情報を伝える「ジャーナリズム」の本質とは?社会問題から娯楽情報まで世の中を広く取材の対象として、情報を伝え興味を喚起するための理論と技術を学び、ジャーナリズムのあり方を考えます。授業を担当するのは、新聞、テレビ、雑誌など各メディア(媒体)での豊かな経験を持つ先生たちです。
本コースではまず、インタビューや調査取材、原稿執筆といった、ジャーナリズムの基礎的な技法を学びます。さらに、国際ニュース、医療・災害・人権といったテーマでの報道検証や取材、あるいはスポーツの魅力を捉えて伝える「スポーツジャーナリズム」の実践、現代の社会・文化を独自の視点で掘り下げる雑誌制作などを通して、専門的な知識とスキルを身につけていきます。新聞や雑誌の制作では企画、取材、撮影、原稿執筆、パソコンを使用した紙面・誌面のデザイン(DTP)まで、すべての制作過程に挑戦し、作品を完成させます。ジャーナリズムについて考え、実践する学びにより、あらゆるメディアに対応し、また世の中の動向を知り、取材し、評価し、表現できるようになることを目指します。
| 必修科目 | 指定科目 | 選択科目 |
|---|---|---|
| コミュニケーション学概論 メディア学概論 マス・コミュニケーション論Ⅰ・II マスコミ学基礎 マスコミ学応用 アカデミック・スキル演習ⅠA・ⅠB アカデミック・スキル演習ⅡA・IIB プレ・キャリアゼミナール 専門ゼミナール キャリアゼミナール 卒業研究 |
メディアリテラシー メディア史 取材学 人工知能概論Ⅰ・II 時事問題Ⅰ・II メディアの法と倫理 |
情報活用論応用 情報社会とメディア ニュース入門 ニュース・新聞論 ジャーナリズム論 ことばと表現(書きことば) ことばと表現(話しことば) 出版コンテンツビジネス論 出版コンテンツプロデュース論 ドキュメンタリー論 スポーツジャーナリズム論Ⅰ・II リポーター論 アナウンス論 国際ニュース論基礎 国際ニュース論応用 スポーツ・ライター、キャスター論Ⅰ・II |
スポーツ新聞の制作現場で、プロの仕事に触れられるチャンスです。「スポーツ記事制作」の授業では、スポーツ新聞『スポエド』を制作。実践を通して取材・原稿執筆のスキルを学ぶことはもちろん、スポーツニッポン新聞社の記者や整理部(紙面の編集・デザインなどを担当する部署)の方から直接指導を受ける機会も。新聞制作の最前線に立つプロから厳しいアドバイスが飛び出すこともあり、取材対象と向き合い、本気で作品に取り組む緊張感が、大きな学びと達成感につながっています。
取材対象は、本学の強化指定部となっているフットボールクラブ(サッカー部)、男子・女子バスケットボール部、そして女子バレーボール部。グループごとに「番記者」となって取材し、リーグ戦に臨む各チームの戦いをレポート。選手の表情を紹介するコラムなども掲載し、読み応えのある新聞を目指します。

スポーツ新聞「スポエド」
本多悟ゼミでは、出版コンテンツ制作の基本となる編集知識を習得し、分析・研究することで一生使える「編集力」を身に付けます。その研究成果として、企画、取材、撮影、執筆、レイアウトなどすべての制作工程を学生が主体となり雑誌制作を行っています。
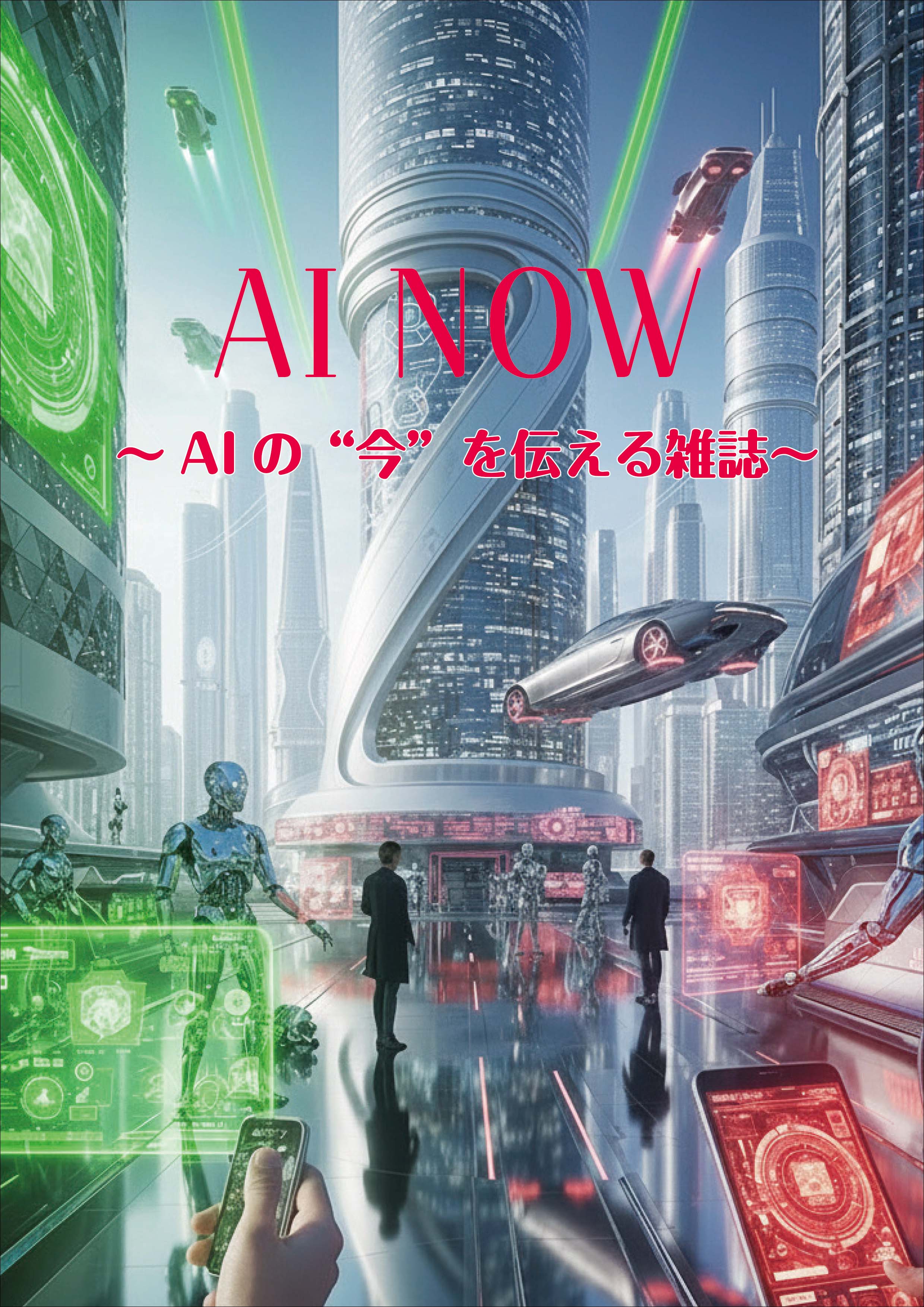 本多ゼミ制作雑誌
本多ゼミ制作雑誌
Student Voice
「演習・実習」では“レトロ自販機の聖地” や独特なお土産自販機など「おもしろい自販機」を特集した雑誌を制作。専門ゼミでは「千葉県の伝統工芸品」をテーマに特集記事を企画、取材や記事執筆に取り組み、千葉日報社主催「CHIBA University Press」に参加しました。たくさんの取材経験を重ねる中で身につけら
れたのは、取材相手の話を引き出し、さらに掘り下げて聞く力。また以前よりも多くのことに興味が広がり、いろいろな関わりを持ちたいと思うようになりました。